生物は理科の中で一番暗記量が多い科目で、いざ勉強してみたら「苦手!」「嫌い!」と感じてしまった受験生はたくさんいます。
- 何から覚えていいか分からない
- とにかく何が何だか分からない
- 暗記したことをすぐ忘れる
これらはすべて「単独暗記」していることが原因です。
今回はその単独暗記とは一体どのようなものなのか、そして苦手な生物を得意にする方法を解説していきます。
生物の苦手を克服するなら
スタディサプリがおすすめ!
基礎固め〜入試対策までレベル別の授業
暗記だけでなく原理を理解できるから
入試やテストで高得点が狙える

\月額2,178円で映像授業が見放題/
目次
生物(生物基礎)の特徴
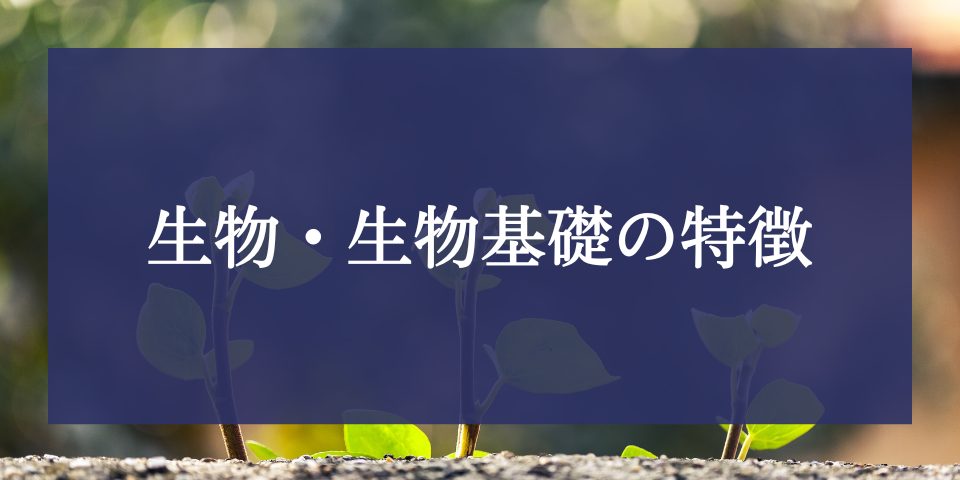
物理や化学よりも暗記量が多い
高校理科の特徴としては以下になります。
暗記量
生物>化学>物理
計算量
物理>化学>生物
つまり生物は暗記量が一番多いものの、計算量は一番少ない科目なのです。
実際に生物を勉強している方なら分かると思いますが、物理のような公式もなければ化学の物質量のような計算問題もありませんよね。
そのため計算が苦手な受験生にとっては生物はとてもありがたい科目でもあるのです。
共通テストで高得点が取りにくい
ここまでの説明を見ると社会科目のように暗記すれば高得点が取れるように思うかもしれませんが、ここに生物の落とし穴があります。
過去のセンター試験、共通テストの平均点を見ると生物の平均点はそれほど高くありません。
2021年を除くと共通テストでは生物・生物基礎ともに平均点が低いことが分かります。
これはセンター試験から共通テストに変わり、より思考力が問われる問題が出題される傾向が強まった影響だと考えられます。
| 物理 | 化学 | 生物 | |
| 2019年 | 56.94 | 54.67 | 62.89 |
| 2020年 | 60.68 | 54.79 | 57.56 |
| 2021年 | 62.36 | 57.39 | 72.64 |
| 2022年 | 60.72 | 47.63 | 48.81 |
| 2023年 | 63.39 | 54.01 | 48.46 |
| 物理基礎 | 化学基礎 | 生物基礎 | |
| 2019年 | 30.58 | 31.22 | 30.99 |
| 2020年 | 33.29 | 28.20 | 32.10 |
| 2021年 | 37.55 | 24.65 | 29.17 |
| 2022年 | 30.40 | 27.73 | 23.90 |
| 2023年 | 28.19 | 29.42 | 24.66 |
※理科基礎は50点満点
生物・生物基礎が苦手・嫌いだと感じる2つの理由
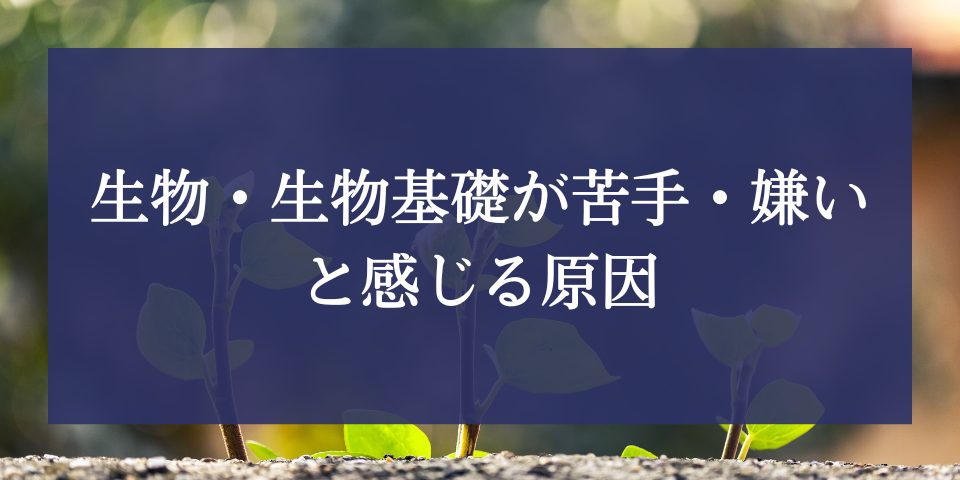
ここからは実際に生物・生物基礎の勉強をしていて苦手・嫌いだと感じてしまう原因について解説していきます。
- 暗記することが多くてすぐに忘れてしまう
- 問題で何を問われているかが分からない
暗記することが多くてすぐに忘れてしまう
生物の用語がなかなか覚えられないことで苦手・嫌いだと感じている受験生が多くいます。
例)光合成
- チラコイド
- ストロマ
- ヒル反応
- カルビン・ベンソン回路
- デンプン
- スクロース など
光合成一つとっても上記のように覚えなければいけない生物の用語はたくさんあり、何が何だか覚えられないと感じてしまいますよね。
覚えても別の用語を覚えているうちにすぐに忘れてしまうということも多々あるでしょう。
そうすると一つ暗記している間に、別の一つを忘れているようで、前進せずにひたすら足踏みしている感覚に陥ってしまいます。
勉強しても何も成績に直結していないように感じて、生物が苦手・嫌いと感じてしまうのです。
問題で何を問われているかが分からない
これは先ほどと重複する部分もありますが、問題で問われている意味が分からないという受験生もいます。
そのように感じる主な理由は以下です。
- 問題文に出てくる用語が分からない
- 生物用語を使って長文で出題されると頭が整理できない
- グラフや図から必要な情報が読み取れない
生物・生物基礎の勉強を始めても、いざ問題を解こうと思ったら「問題の意味が分からない」と感じてしまうとやる気がなくなりますよね。
数学でいきなり応用問題を出されて、何から手を動かしていいか分からない状況と似ています。
一度このようなことを感じてしまうと生物が苦手・嫌いだと感じてしまうのです。
苦手を克服して生物・生物基礎を得意にする方法

用語を覚えられない原因は単独暗記をしているから
生物が苦手・嫌いだと感じている受験生のほとんどは用語を単独暗記しています。
単独暗記とは英単語((例)create=作り出す)のようにそれぞれの用語を単独で暗記しようとする方法です。
チラコイド=葉緑体の膜構造
ストロマ=葉緑体の液体部分
ヒル反応=光合成で水の分解により酸素とNADPHが生成されること
このような覚え方をしていては全く意味はありませんし、成績が上がることはないでしょう。
実際に大学入試問題で「ヒル反応とは何か答えよ」のような、単純に知っているかどうかの知識を問われる問題はほとんど出題されることはありません。
用語の暗記の前に、まずは全体像を把握する
生物・生物基礎の勉強を始める時に用語の暗記から始める受験生がほとんどですが、これは間違いであることを説明しました。
生物・生物基礎の勉強を始める際は、その単元の全体像を把握することから始めなければなりません。
具体的には光合成を例に解説していきます。
光合成には葉緑体のチラコイドやストロマまでの反応があり、その中には様々な用語や化学式がでてきます。
しかし、これらを一気に覚えようとするのではなく、まずは光合成とはどういったものなのか、全体像を理解する必要があります。
- 葉緑体が光を浴びることで化学反応が起き、NADPHとATPを生成する
- その際に水が分解されて酸素が放出される
- NADPHとATPはカルビン・ベンソン回路に受け渡される
- そこで二酸化炭素が固定され有機物が固定される
これが中学校の理科で学んだ、水と二酸化炭素から水素と養分を作り出す流れなのです。
このように、まずは簡単にで良いのでどのような現象が起きているのかを把握しましょう。
この時に覚えた用語はせいぜいNADPH、ATP、カルビン・ベンソン回路の3つぐらいでしょう。
用語は単独暗記ではなく、理解した内容から関連暗記させる
上述したように、用語を暗記する前にまずは全体像を把握します。
そして次に用語を暗記していくのですが、この時に先ほどのようにそれぞれを独立して暗記するのではありません。
用語が、理解した全体像のどの部分に当てはまるのかを関連させながら暗記していくのです。
- チラコイド=葉緑体の膜構造
→先ほどの光合成の全体像の1〜2が起きる場所 - ヒル反応=光合成で水の分解により酸素とNADPHが生成されること
→先ほどの光合成の全体像の1〜2の反応 - ストロマ=葉緑体の液体部分
→先ほどの光合成の全体像の4が起きる場所
このようなことを理解しながら暗記すると
「光合成の全体像の1〜2はヒル反応と呼び、葉緑体のチラコイドで起きる。3でチラコイドからストロマに受け渡され、4はストロマで起きている」
と自分の中で整理することができるのです。
このような覚え方をすることで、用語を忘れることも少なくなってきますし、問題を見たときに何を問われているか分からないなんてことは起きなくなるのです。
人に説明できるぐらい現象を理解する
全体像を把握した後に、用語を関連暗記できたらそれらの知識をつなげて人に説明できるレベルまで理解を深めましょう。
実際に友達などに教える必要はありませんが、口に出して説明してみてください。
そうすると理解していたつもりでも「これとこれってどう繋がっているんだ?」と感じるポイントが出てきたりします。
そういった疑問はどんどん出てきて問題なく、それを教科書や参考書で調べて解決することでより理解を深めていくことができるのです。
人に説明できるぐらい理解していれば、自然と頭の中でその現象のイメージ図を作り上げることができます。
あとは、全体像の把握と用語の関連暗記ができた段階で問題集に取り組んでみると、自分が理解できているポイントとそうでないポイントが明確になります。
このようなやり方で勉強を進めていくと、生物がどんどん得意になり好きになってくるので是非実践してください。
生物の苦手を克服するなら
スタディサプリがおすすめ!
基礎固め〜入試対策までレベル別の授業
暗記だけでなく原理を理解できるから
入試やテストで高得点が狙える

\月額2,178円で映像授業が見放題/




